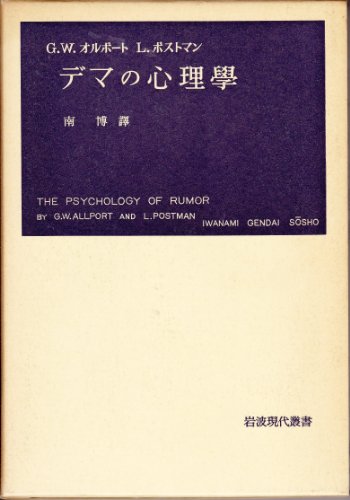予言、第六感、虫の報せについて
かつてロンドンに有名な手相見の女がいた。なんでも、よく当たるというのでかのウィンストン・チャーチルも彼女から助言をもらっていたという。そこで作家オスバート・シットウェルの友人であった士官たちが手相を見てもらったところ、彼女はなぜか突然、彼らの手を押し返して叫んだ。
「わからない、また前と同じだわ! あと二、三月で生命線が切れて、何も読み取れない!」
なんだ大した手相見じゃないな、わからないのでそんな言い逃れをしているんだ、と友人たちは思った。しかしこの話を聞いたシットウェルは、これは何の前兆であろうかといぶかしんだ。
この「事実」が起きたのが1914年だったといえば、勘のいい読者はすぐオチに気付くかも知れない。まもなく第一次大戦が勃発し、彼らはみな数か月後に戦死してしまったのである。

コリン・ウィルソンはシットウェルのこの話を紹介したあとに続け、「かなり多くの人は、この話にはいくらかの真実性はあるが、何らかの点で誇張されていると感じるのではないか」と述べている。また「大部分の人は(中略)さして重要なことではないと考えるだろう。少なくとも、これについて考えてみようという気を起こさない」という。
コリン・ウィルソンがこの話について本当に言いたかったことは、少し後の頁に出てくる。いわく、
私たちの周囲には「意味」が浮遊しているのであるが、通常は、その意味から私たちは習慣や無知や五感の鈍さによって遮断されている、という認識である。いわゆる秘教(エソテリック)の伝統は、あるいは無知な蛮人どもの迷信以上のものではないかもしれないが、同時にそれは、日常の陳腐さの彼方に達する意味をふと垣間見る経験の一つ、人間というラジオが未知の振動をキャッチする瞬間というものを説明する試みにもなりうるであろう。
(コリン・ウィルソン『オカルト』、以下太字は安田による)
つまりこの手相見は、われわれのような日常生活に埋没した意識の持ち主には感知できない何らかの情報、予知をも含むその情報を受信していたのだ、というわけである。
通常は感じ取れないものを感知しようとする営為、という意味では前回ブログに書いた「微分回路的認知」とも共通するところが多い。
わざわざ前回のブログを読まなくてもいいようにざっくり書いておくと、「微分回路的認知」とは強い不安や恐怖によって、なんとか状況を改善しようと感覚計器を研ぎ澄まし、普段なら気付かないような微細な状況の変化からも情報(とくに予兆)を感じ取ろうとする認知モードのことである。健常者でも切羽詰まると微分回路的認知が前景化するが、とくに統合失調症者は慢性的に微分回路的認知が前景化しており、それによって妄想や幻覚を生み出しているという。
もちろん妄想や幻覚自体は他の原因でも起こりうる。いずれにせよこうした見方を採るならば、シットウェルの話を超自然的な能力の存在を示す傍証のひとつだとするのは疑わしい。手相見がなにを思ってそう言ったのか、という内在的な論理ついてもそうだが、そもそも「作家」の友人たちが手相見を訪ねたというこの話自体が、どの程度事実に基づくものなのか?(これについては後ほどまた述べる)
コリン・ウィルソンによれば、科学が今日まで捉えそこなっているこうした潜在能力に我々が目を向けそして覚醒すれば、色々と凄いことになるというかハジマルというのだが、果たしてそうなのだろうか。今回はそれについて検討を加えてゆく。
*
似たような別の話に目を向けてみよう。例えばこちらは女手相見ではなく尼僧であり、また第一次大戦の勃発ではなく、第二次大戦の終結についての話である。
この奇妙な話は去年の冬、このあたりに広まった。わたしはこの話を友人から聞いた。その友人はシカゴの友人から、またその人は近所の人から聞いたという。
タクシー運転手のマイクは、一二月の初めに乗せた不思議な乗客についてこんな話をした。シカゴの繁華街を流していて、カソリックのかなり年配の尼僧を乗せた。彼女は〇〇通りへ行って欲しいと言った。マイクはカーラジオをつけっぱなしにしていた。二人は真珠湾攻撃についてしばらく話した。「この戦争はあと四ヵ月も続かないでしょうね」と彼女は言った。しばらく走って、マイクは彼女の言った所へ車を乗りつけ、運転席から降りて彼女のためにドアを開けようとした。ところが、何と彼女は消えていたのだ。
マイクはその小柄な年寄りの尼僧が料金を踏み倒して逃げたのかと思い、そこの修道院に話をつけに行った。担当の修道院長に「どんな人だったのですか」と尋ねられたので、マイクはその金を払わずに消えた尼僧について説明した。だが、院長は今日は誰も街には出ていないと言う。すると偶然、院長の机の後ろにかかっている写真が目に入った。「この人ですよ」とマイクは言い、これでやっと料金を払ってもらえると思った。だが、院長は静かにほほえんで言った。「でも、この人はもう一〇年前に亡くなっていますよ」
(ジャン・ハロルド・ブルンヴァン『消えるヒッチハイカー』)

尼僧という職業はいかにも超自然的なメッセンジャーにふさわしく、女手相見と同じように物語に「らしさ」を与えている。またどちらも女であるということも霊媒的性質の強調であろう。
ブルンヴァンによればこの事例は1941年12月に採集されている。つまり興味深いことに予言としては外したことになる。あの世から出張してわざわざご託宣を垂れたわりには、常人のあてずっぽうと大して変わらないようだ。
次の話も戦争の終結をめぐるものである。
インディアナ州ブラフトン発一月二五日。インディアナ州エルウッドのミセス・ロバート・ナディンはその日そこでこのような話をしてくれた。彼女と夫は、妹のミセス・オーガスト・レイムグルーバーを訪ねてインディアナポリスへ車を走らせていた。その時、ひとりの老人が道を歩いていたので乗せてあげた。車を降りる時、老人は「わたしにはご好意に対してお払いするお金がありませんが、あなた方が聞きたいと思うことに対して何でもお答えしましょう」と言った。ナディンさんは「戦争はいつ終わるでしょうね」と聞いた。「簡単なことですよ。六月には終ります」と老人は答えた。ナディン夫妻は笑ったが、その老人は自分の予言を繰り返した。「これは本当のことですよ。これからあなた方が家にたどりつくまでに車に死体を乗せることになるのと同じくらい、本当の話です」と言った。
インディアナポリスの近くで、救急車がナディンさんの車を追い越していったが、スリップして溝にはまり横転してしまった。救急車の運転手はナディンさんに患者をインディアナポリスの病院へ運んでくれと言った。ところが、その病人は着く前にナディンさんの車の中で死んでしまった。
(同書)
こちらは「ザ・フランシスコ・クロニクス」紙に1942年1月に掲載された記事である。残念! またもや外れだ。もっともこの性別も素性もわからぬ老人は、車に死体を乗せることになるという、よりありそうもない予言のほうは見事に「当てて」いるが。
これらの話はシットウェルのいちおう実話という体裁の「回想」とは違い、都市伝説にカテゴライズされている。おそらく戦争がもたらす強い緊張と不安、終戦への願望がこうした都市伝説を生んだのであろう。そういう意味ではこれらの話も「微分回路的認知の前景化」に寄せた説明が可能かも知れない。
都市伝説の生成は統合失調症とは違って集団的なプロセスだが、テレンス・ハインズの集団ヒステリーについての議論などを見ると、妄想や幻覚は必ずしも集団になれば抑制されるというものでもないようだ。むしろ私も見た、聞いた、と集団によって妄想や幻覚が増幅される場合もしばしばあるのである……
*
デマ研究の第一人者であるオルポートとポストマンの挙げる事例では再び女占い師が登場する。また車に死体を乗せることになる、というモチーフもブルンヴァンと共通している。
ある占い師は六ヶ月以内にヒトラーが死ぬだろうと予言したという調子の、馬鹿々々しい話が、全国にひろまったことがある。この予言を告げられた男は、疑わしげな素振りを見せた、とこの話は続いている。するとこの女占い師は、そのお告げにこうつけ加えた。「そうですよ。六ヶ月以内にヒトラーは確かに死にます。それから近い将来のことですが、あなたの自動車には死体がおかれるはずですが、これも同様に確かなことですよ。」それからしばらくたって、ドライヴ中だったその疑い深い男は道端で怪我人に出会い、病院に連れて行くために車にのせた、ところが病院に着いてみると、その男は既に車内でこと切れていたということである。
(オルポート/ポストマン『デマの心理学』)
オルポートとポストマンはこうした話を「願望デマ」と呼んでいる。そしてここが重要なのだが、願望デマは「ドイツの破局が目前に迫るまでは、あまり見られなかった」が1945年の4月になると「洪水のように流れ始め」たという。

してみると、ブルンヴァンが挙げた事例ではいずれも予言を外していたものの、全体として見ると当たった予言(デマ)のほうが多かったということになる。これをどう解釈すればよいのか。やはり占い師や尼僧などの特殊な人には(あるいはそういう都市伝説を伝言ゲームで作り上げた人たちには)なんらかの予知能力、第六感が備わっていたのだろうか?
おそらくそうではない。人々は(大本営発表よりは信頼できたであろう)報道や暮らしのなかでの物資や市場にたいする感触、戦地から漏れ伝わる話等々によって、実際に勝利が近いのだとおおかたの察しがついていたのだろう。
結局のところ、はっきり意識せぬとも「なんとなく察しがついていた」というのが、我々の第六感とか虫の報せと呼ぶものに関係しているのではないか。
このことに思い至ったのは、吉本隆明が『共同幻想論』のなかで展開しているある議論に接したためであった。
*
吉本隆明は『共同幻想論』所収の「憑人論」において、柳田國男『遠野物語』のなかから予兆、虫の報せに関する話を五つほど抜き出している。そのなかの一つは次のようなものだ。
或る男が奥山に入って茸を採るため、小屋掛けをして住んでいたが、深夜に遠い処で女の叫び声がした。里へ帰ってみると同じ夜の同じ時刻に自分の妹がその息子に殺されていた。
(柳田邦男『遠野物語』)
遠く離れた麓から、届くはずのない妹の断末魔の叫びが聞こえたという。
この挿話について、吉本は超自然的な解釈を採らない。彼によればこういった予兆譚の背後には、かならず入眠幻覚に類する心の体験があるという。
入眠幻覚とは、半睡状態のときに見る、ひじょうにリアリティを伴った幻覚のことだ。身も蓋もない言い方をすれば「寝ぼけて見たもの」ということになる。男が聞いた妹の叫び声もその類いだというのだが、なぜそんな内容の入眠幻覚を見たのかといえば、
フロイト的にいえば『遠野物語』の村民は、じぶんの妹が息子の嫁と仲が悪く、板ばさみになった息子は母親を殺すか嫁を離別するかどちらかだとおもいつめていることを予め知っていたために、山奥で妹の殺される叫び声をきいたのであろう。その時刻がほんとうに妹が息子から殺される時刻と一致したということにはさしたる重要な意味はない。もっと条件を緊密においつめてゆけば、おもいつめた息子が母親を殺すのは今日か明日かという時間の問題であることをも、山奥にいたその村民は知っていたとかんがえられるからである。
(吉本隆明『共同幻想論』)
と吉本は云う。
なんとなく察しがついていたことによって入眠幻覚がそのような内容になった、というわけだ(ちなみにこの幻聴を微分回路的認知の前景化のためだと解釈することも容易だ。妹が殺されることが充分予想できており、しかも深夜の山奥で一人過ごしているというのは、強い不安と恐怖とともにあったはずである。そしてこの解釈は「なんとなく察しがついていた」解釈と両立しうる)。
こうした予兆、虫の報せについての話はひじょうに数多い。遠方にいる近親者や友人が亡くなる前にふと現れたり、その人に関係する持ち物がどうにかなったりする例のパターンだが、霊魂やテレパシーといった超自然的解釈以外で考えられるのは今のところ、この「なんとなく察しがついていた」パターンと「後から思えば」パターンが有力ではないかと思う。超自然的解釈は「どうしてもそれ以外の解釈ができない時」にはじめて検討すればいいのではないか。
ちなみに「後から思えば」パターンというのは、人間は思った以上にさまざまなことを思い浮かべては忘れており、何か重大なことが起きた時に、思い返せばそれなりに「虫の知らせ」のようなものが見つかってしまうのではないか、ということである。たとえば飛行機に乗る人は「もし墜落したら」ということを一瞬くらいは考えるのであり、また年老いた親や幼い子供やかけがえのないパートナーのことを考えるとき、その人の死について少しくらい頭をよぎるのは当たり前のことではないか、ということだ。
冒頭のコリン・ウィルソンが挙げているシットウェルの回想には、こうした「後から思えば」パターンを疑うべき箇所がある。というのもウィンストン・チャーチルは1914年にはいち海相にすぎなかったのである。となると、シットウェルはかなり後になってからチャーチル首相の海相時代のお気に入りの手相見の名前を知ったのだろうか。そして、偶然にもそれが友人たちを診た手相見と同一人物であることに気付いたのだろうか。
むしろこう考えたほうが自然なのではないか。つまりこの話はまったくの作り話ではないにしても、幾つかの事実の断片、当時の噂、作家的想像力などを組み合わせ構成したものなのではないか、と。
こうして見てゆくと、一見不思議に思える話も、どうしても予知能力や第六感、虫の報せといった超自然的な説明を持ち出さなければ理解できぬものではない。
むしろ、今回見てきたような話をつくりあげる人間の心の作用のほうが、僕には不思議で、解き明かしたくなる魅力を持っているように思える。

- 作者:コリン・ウィルソン
- メディア: 文庫

- 作者:コリン・ウィルソン
- メディア: 文庫

消えるヒッチハイカー―都市の想像力のアメリカ (ブルンヴァンの「都市伝説」コレクション)
- 作者:ジャン・ハロルド ブルンヴァン
- 発売日: 1997/02/01
- メディア: 単行本

- 作者:柳田 国男
- 発売日: 1955/10/05
- メディア: 文庫
『遠野物語』については、「山の人生」とカップリングされている岩波文庫版で読む人が多いだろうが、「遠野物語拾遺」とカップリングされている角川文庫版も捨てがたい。なお「拾遺」のほうが日露戦争など、やや時代の新しいエピソードが多め。

- 作者:吉本 隆明
- 発売日: 2020/06/12
- メディア: 文庫